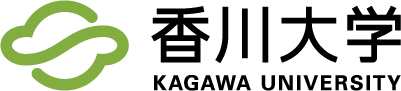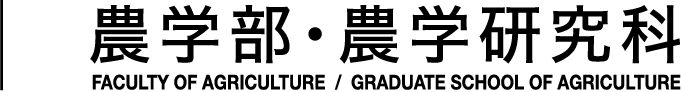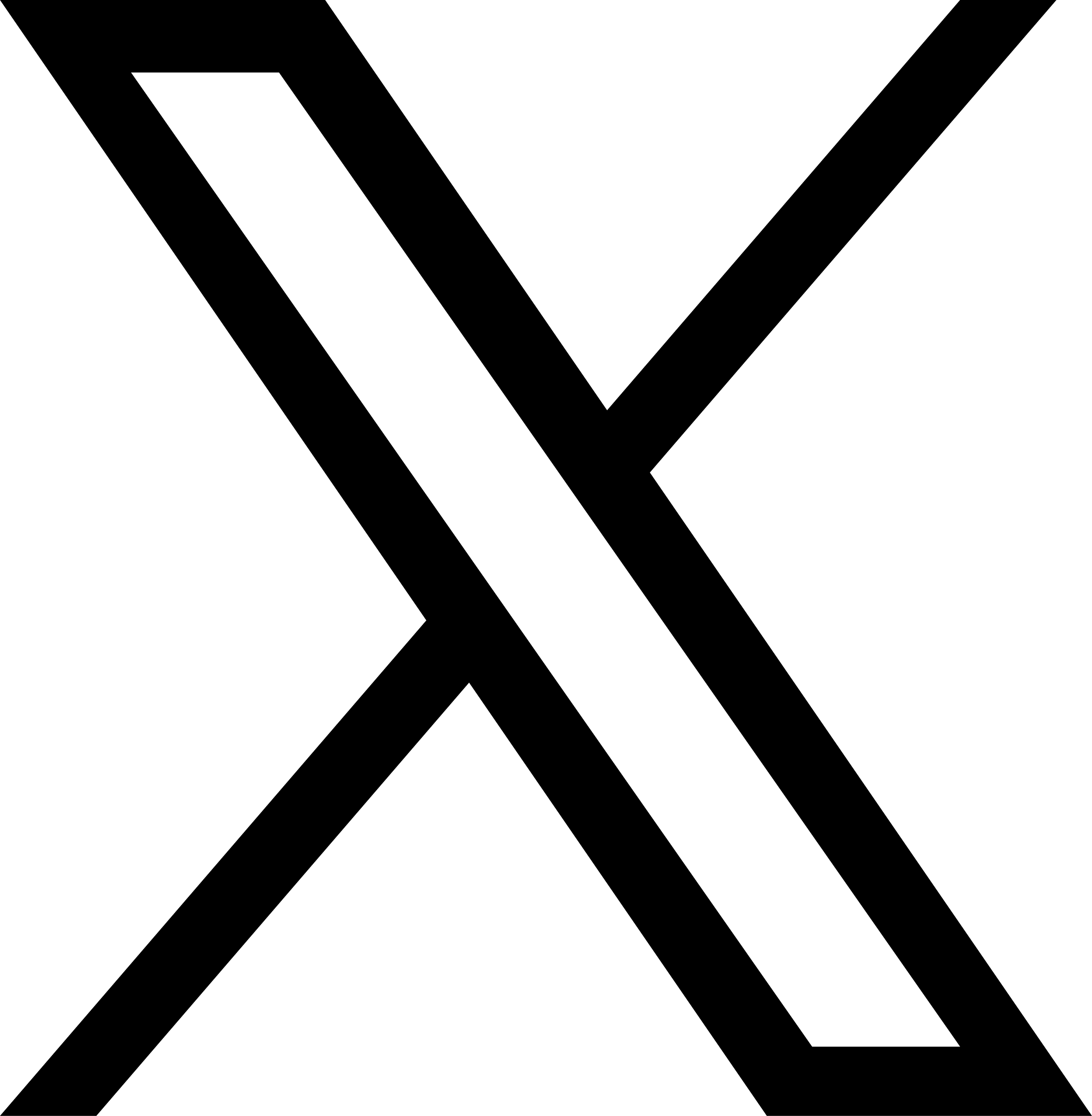香川大学農学部・大学院農学研究科のホームページにお越し頂きましてありがとうございます。香川大学農学部は、1903年に創設された木田郡立乙種農学校を起源とし、その後香川県立木田農林学校、香川県立農科大学など数回の変革を経て、現在の香川大学農学部になりました。2023年4月で開学120周年を迎えました。同年7月には120周年記念式典が農学部キャンパスで盛大に開催されました。伊藤三木町長、淀谷香川県教育長をはじめ多くの来賓者、池戸会(同窓会)からは岩田会長はじめ多くの卒業生、本学からは筧学長(当時)、教職員、現役の学生が出席しました。120年に及ぶ教育研究の軌跡を共有するとても良い機会となりました。詳しくは香川大学農学部開学120周年記念 (kagawa-u.ac.jp)をご覧ください。
120年に及ぶ長い歴史のなかで1万人を超える卒業生を社会に輩出してきました。この歴史と伝統は今に受け継がれていますが、時代に合わせて進化して現在の香川大学農学部・大学院農学研究科の体制になりました。現在農学部で行っている教育(学び)の特徴と、農学研究科で行っている研究の特徴を紹介させて頂きます。

農学部長 小川雅廣
まず、学部教育ですが、1年次は全員が農学という学問に共通する基礎教育を受けます。2年次になると「先端生命科学」、「アグリサイエンス」、「フィールド環境」、「バイオ分子化学」、「食品科学」の5つのコースから学びたいコースを選び、専門的な知識や技能を学びます。3年次になると研究室に分属し研究活動を始めますが、意欲のある学生は1年次からでも研究室で研究活動をすることができます。もう一つの特徴は国際教育です。本学農学部では「科学英語」、「国際英語演習」、「ベーシックバイオロジー」、「ベーシックケミストリー」など英語で学ぶ専門科目を他大学農学部と比べても多く開講しています。それらの英語関連科目を履修した学生のなかにはTOEIC L&Rの点数が200点以上伸びた者もいます。2024年度からは、「International Presentation: Thesis」という科目が新たに開設されます。これを履修することで自分の研究内容を英語で口頭発表できるようになります。修了要件を満たした者には卒業時に国際科学コミュニケーションプログラムの修了証書が授与されます。
次に、農学研究科の研究の特徴を紹介します。同研究科は応用生物・希少糖科学専攻の1専攻からなります。専攻名に入っている希少糖は、初めて聞く人もいらっしゃると思います。希少糖とは「自然界に微量にしか存在しない単糖とその誘導体」のことで、本学農学部の何森健教授(現在は名誉教授)によって提案された造語ですが、今では広辞苑にも掲載され、認知度が上がりつつあります。自然界に微量にしか存在しなかったはずの希少糖ですが、何森教授が発見した微生物酵素によって大量に生産できるようになり研究は大きく進展しました。50種類以上ある希少糖のなかのいくつか(D-アルロースやD-アロース)には生活習慣病の予防効果や抗がん作用が見つかっており、日本のみならず世界でも注目されています。この希少糖研究を先導してきたのが本学農学研究科と農学部です。現在は、食品、農薬、医薬品、その他の工業製品への応用を目指して、本学医学部、創造工学部や民間企業と連携して研究を進めています。農学研究科には希少糖以外にも「食糧」、「環境」、「生命科学」の分野で魅力的な研究が数多くあります。詳しくは研究紹介 | 香川大学農学部 (kagawa-u.ac.jp)をご覧ください。
最後にグローバル教育について紹介します。現在、東南アジアを中心に約10か国からの留学生約30名が農学部、農学研究科(修士課程)及び連合農学研究科(博士課程)で学んでいますが、コロナ禍も明け、2024年10月から留学生と日本人学生が共学する新たなコース(食と環境保全特別コース)が農学研究科に開設されます。これにより農学部キャンパスの留学生は増えると考えています。本特別コースでは、食料と環境保全関連の科目を英語と日本語で提供します。コースに在籍する学生は日本語で提供される科目と英語で提供される科目の両方を履修することになるので、留学生は日本語力が、日本人は英語力が鍛えられます。これにより、専門性とコミュニケーション能力を備え、多様性を受け入れられる真のグローバル人材を社会に送り出すことができると考えています。
香川大学農学部・農学研究科の教育・研究・国際活動の情報はホームページに随時更新していますので訪れていただければ幸いです。